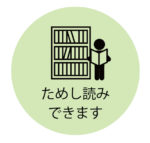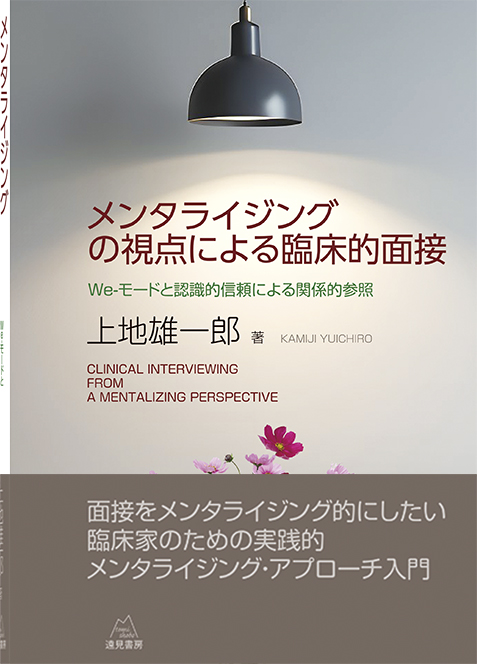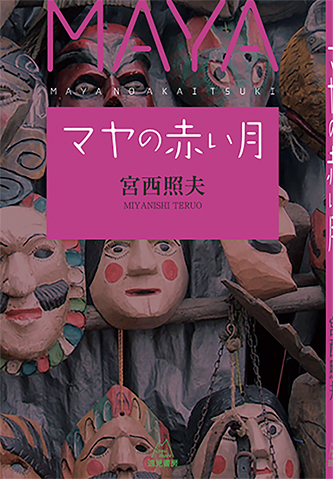N:ナラティヴとケア 第16号 ナラティヴの政治学──対人支援実践のために
| 編者 | (立正大学社会福祉学部社会福祉学科)安達映子 編 |
| 出版年月 | 2025年1月 |
| ISBN | 978-4-86616-214-0 |
| 判型 | B5判並製 |
| ページ数 | 92 |
| 定価 | 1,800円(+税) |
内容紹介
被支援者の置かれた環境だけではなく,支援の関係性や援助者同士などさまざまなところに現れる権力(パワー)の問題。対人支援の仕事をするものは,その権力性に気づく必要がある。その権力の非対称性を越えようとするときに必須なのが,「ナラティヴ」の考え方である。
この特集は,支援の場に潜む政治学に気づく支援者たちによって書かれたものである。過激かつ刺激的な論考が集まっている。
主な目次
「政治学としてのナラティヴ・セラピー」という場所から─特集によせて ◇ 安達映子(立正大学社会福祉学部社会福祉学科)
巻頭座談会 臨床のなかの/をとりまく政治学 ◇ 安達映子(立正大学社会福祉学部社会福祉学科)+伊藤絵美(洗足ストレスコーピング・サポートオフィス)+田中ひな子(原宿カウンセリングセンター)
ミソジニーをほどく──家父長制に抗するナラティヴ・プラクティス ◇ 西井 開(立教大学大学院社会デザイン研究科特別研究員(PD))
心理臨床の二次加害リスク──被害者支援の現場から考えること ◇ 齋藤 梓(上智大学総合人間科学部心理学科)
“弱い支援者”の技法──“支援しない”ことを“する” ◇ 荒井浩道(駒澤大学文学部社会学科)
世の中のせいにして,世の中を変える──反自己責任のソーシャルワークとソーシャルアクション ◇ 鴻巣麻里香(KAKECOMI/福島県スクールソーシャルワーカー)
支援実践から問う家族規範/ジェンダー規範 ◇ 新藤こずえ(上智大学総合人間科学部社会福祉学科)
臨床あるいはマンガから見える日常性のポリティクス ◇ 阿部幸弘(北海道精神保健推進協会こころのリカバリー総合支援センター)
地域精神保健の立場から「政治」について語ってみる──「臨床のなかの/臨床をめぐる政治学」へのリフレクション1 ◇ 伊藤順一郎(メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ)
「呼び名」を巡るセラピストの物語──「臨床のなかの/臨床をめぐる政治学」へのリフレクション2 ◇ 赤津玲子(龍谷大学大学院文学研究科)
セラピーの社会論的転回とナラティヴの政治学──「臨床のなかの/臨床をめぐる政治学」へのリフレクション3 ◇ 野口裕二(東京学芸大学名誉教授)
気管切開の政治学──隠喩と換喩 ◇ 小森康永(愛知県がんセンター)
編集後記
「ナラティヴの政治学」という今回のテーマ,依頼状にはやや熱量高めの?企画趣旨を添えました。思い返すと気恥ずかしいのですが,その呼びかけに,想定を軽々と超えて真摯に応えてくださるものが今ここに集まっています。論考も鼎談も,一人ひとりの地の声がしっかりと響いて率直です。それに留まることなく,それぞれの仕事の厚みに裏打ちされて実践・研究の前線が描かれ,学びが多く,思考が刺激されます。
そもそもこのテーマを選んだのは,呼びかけられていることにわたし自身が応えていないというモヤモヤがあったからでした。編者という立場で複数の声との共鳴のうちに,小さな応答の機会をいただけたことに感謝します。国内外の情勢を見渡すとき,ナラティヴそのものが孕む政治性,リスクとしてのナラティヴなど,十分に踏み込めなかったことも多くあります。「ナラティヴの政治学」をめぐる会話をさらに続けよう,あらたな呼びかけが早くも生まれています。(安達映子)
執筆者一覧
【50音順】
赤津玲子(龍谷大学心理学部)
安達映子(立正大学社会福祉学部社会福祉学科)*
阿部幸弘(北海道精神保健推進協会こころのリカバリー総合支援センター)
荒井浩道(駒澤大学文学部社会学科)
伊藤絵美(洗足ストレスコーピング・サポートオフィス)
伊藤順一郎(メンタルヘルス診療所しっぽふぁーれ)
鴻巣麻里香(KAKECOMI/福島県スクールソーシャルワーカー)
小森康永(愛知県がんセンター)
齋藤 梓(上智大学総合人間科学部心理学科)
新藤こずえ(上智大学総合人間科学部社会福祉学科)
田中ひな子(原宿カウンセリングセンター)
西井 開(立教大学大学院社会デザイン研究科特別研究員(PD))
野口裕二(東京学芸大学名誉教授)
*編者
新刊案内
「遠見書房」の書籍は,こちらでも購入可能です。

最寄りの書店がご不便、あるいはネット書店で在庫がない場合、小社の直販サービスのサイト「遠見書房⭐︎書店」からご購入ください(store.jpというECサービスを利用しています)。商品は在庫のあるものはほとんど掲載しています。