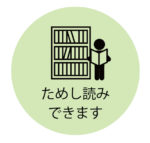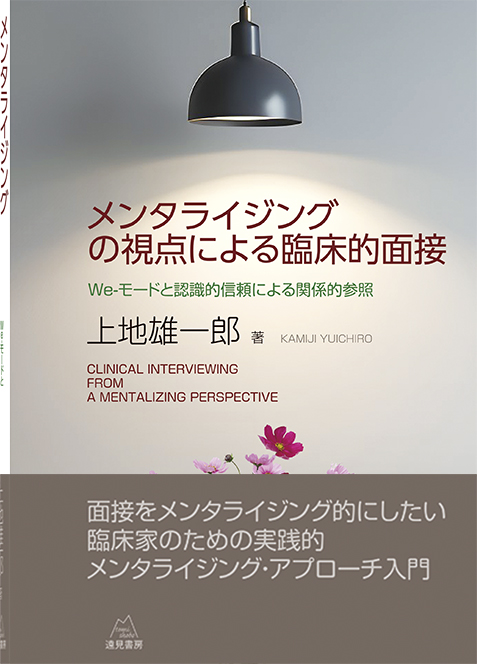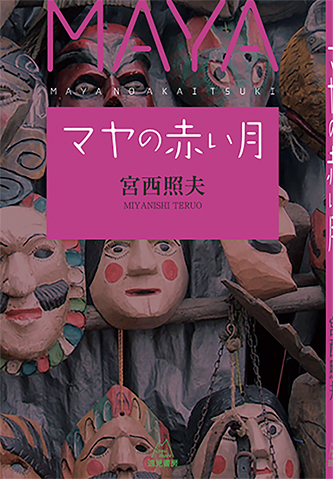ナラティヴ探究──ベイトソンからオープンダイアローグへのフィールドノート
ナラティヴ探究──ベイトソンからオープンダイアローグへのフィールドノート
| 著者 | 野村 直樹 |
| 出版年月 | 2025年4月 |
| ISBN | 978-4-86616-218-8 |
| 判型 | 四六判並製 |
| ページ数 | 198 |
| 定価 | 2,100円(+税) |
内容紹介
ナラティヴの世界を探究する文化人類学者 野村直樹の論考集。グレゴリー・ベイトソン,ナラティヴの認識論,ナラティヴ・セラピー,無知の姿勢,時間論,グーリシャンとアンダーソン,オープンダイアローグにつながるナラティヴの世界を試行錯誤しながら進んだ軌跡がまとめられている。
刺激的なナラティヴの世界へようこそ。
主な目次
まえがき
グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson)の主著Steps to an Ecology of Mindが、『精神の生態学へ』と題して岩波文庫(佐藤良明訳)から新たに出版された。五〇年前サンフランシスコ州立大学のブックストアで二ドル五〇セント出して買ったそのペーパーバックがいま手元にある。帰国してからだいぶ経った二〇〇七年、第一回のベイトソンセミナーを京都で開いた。そして、今年その六十五回目をやはり京都近郊で行った。セミナーでは、この本からどれか一章を取り上げ、参加者が車座に座り意見交換と討論を中心に進める。参加者の専門は多岐にわたる、精神医療、看護、心理臨床、福祉、教育、法律、言語学、社会学、人類学、地域研究、アートなど。心理系ではベイトソンになじみの薄いひとも多いかもしれない。しかし、ことヒトのコミュニケーションに関してならば、ベイトソンを踏まえておいた方がよいとぼくは常々思っている。
ベイトソンの出自は生物学と人類学である。そこからコミュニケーション理論、精神医学、進化論、美学など科学哲学の諸領域を渡り歩いた。それはナラティヴの思想に深く関わり、「双方向性」(mutuality)と「言語的稼働性」(linguistic mobility)という見地からナラティヴを牽引する役を果たす。「双方向性」は頭で理解する概念というより、むしろ語学の習得に近い。社会科学で言う大抵の概念は一方向の「属性言語」でできている、理性、パーソナリティ、発達、権力、疾患、価値観、技能など、つまり個や主体を形容する言葉群である。これはこれなりに言語として成立している。しかし、コミュニケーションの言語は違う。外国語が一朝一夕でマスターできないのと同様、ベイトソンの「関係性言語」も地道ないわば外国語学習を要求する。「言語的稼働性」とはコンセプトが「動き」を持っていることだ。ダブルバインドはコミュニケーションの「動き」を形容した「関係性言語」である。右の「属性言語」を見てみようか、概念が停止しているのがよくわかると思う。ナラティヴは「関係性言語」という文法に沿って話されているので、この文法を無視するとナラティヴは危うくなる。
ナラティヴを多くのひとはふつう誰かの語りとして「一人称」で考える。語りの内容、意義、示唆、主張、矛盾、強調点、などとして。しかし、それでは対象とする個に焦点を当てただけである。ナラティヴは「二人称」の双方向行為であって、例えば、研究者あるいは治療者ならその人もまた分析の対象になるわけだ。患者だけあるいは家族だけの語りを分析しても、それはナラティヴにはならない。ナラティヴはコミュニケーション現象の中でとりわけ言語的側面に光を当てることによって見えてくる、人と人の関係性の動きに関するサイエンスのことである。それは双方向性を基本とするインターアクション、つまりミハイル・バフチンのいうところの対話としてみていくとする認識論が徹底され、それに伴い研究者自身が研究の対象になって初めて出てくる領域である。文学としての物語、村の古老の語り、語り部による昔話、裁判証言の語り、それらはナラティヴと言えなくもないが、それらは昔からあったものである。この新領域が言わんとするナラティヴは、社会的役割を超えて水平な立場での対話が、両者の中にそれまでなかった新たな解釈を生み出し、今まで語られなかった部分、思いつかなかったストーリーライン、新奇なアイデア、大胆な仮説、自分の再発見などを育む行為のことである。「私」自身の変化というリスクを背負った行為のことである。
さて、ポストモダンの思想は、ジャン・フランソワ・リオタールの『ポストモダンの条件』以降、いろんな言葉(例、ポスト構造主義、解釈学的アプローチほか)で表現されてきた。そんな中「ナラティヴ」の一語が最もこの思想の本質を伝えるのに適した概念として広く受け入れられるようになった。一九八八年にアーサー・クラインマンが語りに焦点を当てた医療人類学としてThe Illness Narratives(「病いの語り」)を出版し、同年ハーレーン・アンダーソンとハロルド・グーリシャンがFamily Process誌上にHuman systems as linguistic systemsという画期的な論文を発表した。これによってナラティヴという分野の呼び名とそれを下支えする理論的枠組みが用意されたと言える。その二年後のマイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンによるNarrative Means to Therapeutic Ends(邦題『物語としての家族』)が一連の流れを決定的にした。以後欧米ではナラティヴ旋風が巻き起こることになる。わが国では一九九七年に『ナラティヴセラピー─社会構成主義の実践』が初めてナラティヴの語を冠した本として世に出て以降、「ナラティヴ」は急拡大していった。臨床心理学、社会学、歴史学、人類学、看護学、医学、などの分野に波及した。Narrative-Based Medicineという医学領域も飛び出してきた。「ナラティヴ」という言葉や概念は昔からあったはずなのに、なぜこのタイミングで時代のキーワードとして注目され前面に踊り出たのか。その答えの一部はやはりベイトソンにあるとぼくは考える。
一九八〇年代までにはアメリカの社会科学の分野は、時期をずらしながらも、ほぼすべての分野がポストモダン思想の洗礼を受けることになった。人類学においては、クリフォード・ギアーツの『文化の解釈学』(一九七三)をもって応答することになるが、文化人類学それ自体が植民地支配の視座から抜け出ていないとして、その根本から存在意義を問われた時代でもある。フィールドワークの認識論に危機を抱いた人類学者ヴィンセント・クラパンザーノは、あるモロッコ人と自分との肖像画を『精霊と結婚した男』(一九八〇)に描いた。民族誌上、記念碑的な作品である。歴史学におけるヘイドン・ホワイトの『メタヒストリー』(一九七三)や精神分析学のドナルド・スペンスの『Narrative Truth and Historical Truth(物語的真実と歴史的真実)』(一九八二)などもポストモダンの潮流への応答として挙げられ、いずれもそれぞれの分野に再考を促す名著とされた。
家族療法(Family therapy)もまた同じ潮流の中にあった。低迷と行き詰まりの中での試行錯誤から八〇年代後半に至ってようやく光が見えはじめた。その先陣を切ったのが前述のアンダーソンとグーリシャンであった。六〇年初頭から家族療法が大事にしてきたベイトソンの認識論がポストモダン思想の到来を受けて、「治療としての会話、語り」という方法論が編み出されていった。ナラティヴを学問分野として格上げしたのは家族療法である。ホワイトとエプストンの貢献により、「ナラティヴセラピー」つまり「人生という物語を書き換えることが治療」であるとするわかりやすい理論が、「ナラティヴってこういうことなのか」と誰でも分かるような図式で目の前に提示されたことによって、一気にこの概念が使い勝手のよい合言葉として愛用されることとなった。グーリシャンの弟子ノルウェイのトム・アンデルセンは、治療者チームを家族の観察対象にしてしまう先駆的な家族療法に乗り出した。社会科学のありようを変えうる画期的な枠組みの提供である。
しかし、そうして名前が浸透した分、一方でナラティヴはいくぶんその鋭利さを欠いてしまったかもしれない。ナラティヴ理論の表層的な特徴を自らの分野の都合に合わせて取りこむことで、ベイトソン由来の文法、使い方があることが忘れられがちになる――「なんでもナラティヴ」として見ることができるから、と。しかし、ナラティヴはもともと治療に関する分野のじつに切実な危機感から生まれた。それは広い意味での治療的コミュニケーションに関する理論のことと言ったらよいだろう。ただ、その背後に控えているのは、既存の科学の状況を変えようとする意気、新しい価値観、認識論、世界の見方である。家族療法がナラティヴという治療論に行き着いた背景には、先ほどの「双方向性」と「言語的稼働性」、すなわち「関係性言語」があったからと言ってよいだろう。それをもしバフチン流に言い換えれば、言葉は対話の中でその生きた応答として生まれ、評価と応答を含むやりとりの中で主体性を獲得する、となる。そして、「関係性の中で生きている言葉」が対象へ働きかけるその仕方は、ひとつとして同じではない、弾力的でしばしば見通すことも困難であるが、新たな着想や見解を育む可能性を秘める。ベイトソンとバフチンの考え方は見事に一致するため、現在の家族療法の最先端のオープンダイアローグは、ベイトソンとバフチンをその祖先に据えている。言葉は対話の中で生まれる、と聞いたらびっくりするのは言語学者だけではないだろう。これらの思想の徹底は、驚くほど革命的である。
ナラティヴの認識論は、外側からの観察による言説ではなく、内側からの参加経験に基づく説明を頼りにする。そして、それらを聴いていく構えを大事にする。したがってそこでは双方向で水平な会話が可能となるための工夫が必要となるが、「あなたの知っていることを私は知らないので教えてください」という好奇心をもって臨む「無知の姿勢」(Not-knowing)が、会話を成立させる最も有効なスタンスであることをグーリシャンは発見した。おそらくこの発見こそ、ナラティヴ理論の実践としてのもっとも見事な到達点であり、会話の中で生きているわれわれへの永遠の贈り物である。「無知の姿勢」は、会話の過程に現れてくる数々のセンサーによって観測される複雑な情報源から導かれ、単純なスケールによる数字には還元できない。また、それは質的かつローカルで豊かな二人称世界で起こる事件を扱うための方法論でもあり、治療的対話のみならず質的調査全般にも当てはまる哲学的スタンスである。
この本の各章は大方そのようなスピリットで書いたつもりではあるが、このまえがきも含め、読者のみなさんの忌憚のないご批判をいただけたら大変嬉しく思う。本にするにあたり遠見書房の山内俊介さんには大変お世話になった。この場を借りて深くお礼を申し上げたい。
野村直樹
著者略歴
野村直樹(Nomura Naoki)
1950年生まれ。スタンフォード大学大学院文化人類学専攻(Ph.D.)。
名古屋市立大学名誉教授。
主な著書・翻訳書
『みんなのベイトソン』金剛出版、2012
『ナラティヴ・時間・コミュニケーション』遠見書房、2010
https://tomishobo.stores.jp/items/5d888a4c4813731749563c99
『協働するナラティヴ』遠見書房(アンダーソン&グーリシャンとの共著)、2013
https://tomishobo.stores.jp/items/5d888a4e4813731749563cd4
『やさしいベイトソン』金剛出版、2008
アンダーソン著『会話・言語・そして可能性』2001(共訳)、金剛出版
マクナミー&ガーゲン編『ナラティヴ・セラピー―社会構成主義の実践』遠見書房(野口裕二との共訳)、2014
https://tomishobo.stores.jp/items/5d888a4f4813731749563cf6
新刊案内
「遠見書房」の書籍は,こちらでも購入可能です。

最寄りの書店がご不便、あるいはネット書店で在庫がない場合、小社の直販サービスのサイト「遠見書房⭐︎書店」からご購入ください(store.jpというECサービスを利用しています)。商品は在庫のあるものはほとんど掲載しています。