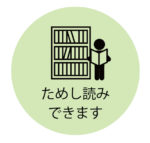ダイアロジカル・スーパービジョン──リフレクションを活用した職場文化のつくりかた
ダイアロジカル・スーパービジョン──リフレクションを活用した職場文化のつくりかた
カイ・アルハネン/アンネ・カンサナホ/オリ・ペッカ・アーティアイネン/
マルコ・カンガス/カトリイナ・レーティ/チーナ・ソイニ/ヤルコ・ソイニネン著
川田美和/石川雅智/石川真紀/片岡 豊 監訳
3,000円(+税) A5判 並製 190頁 C3011 ISBN978-4-86616-199-0
オープンダイアローグから始まった実践であり,哲学である〈ダイアローグ〉。その応用実践の一つがダイアロジカル・スーパービジョンです。
スーパービジョンは,専門家教育のなかで指導者(スーパーバイザー)が被指導者(スーパーバイジー)に職務上の指摘や助言を行うことで,対人援助の世界で行われることが多いですが,北欧にはスーパービジョンの制度が根付き,対人支援だけではなく企業や組織のなかでも外部のスーパーバイザーがつき,コンサルテーションを行っています。
この本は,北欧のスーパービジョン文化とオープンダイアローグの哲学とが出会い,リフレクションから新しいダイアローグをどう育て,個々人の職業人生に生かしたらいいのかを詳細にまとめたものです。
対人援助職やその施設だけではなく,コミュニティ指導者や管理職などのリーダー,コンサルテーションを行っている方,スーパーバイザーなど多くの方に読んでいただきたい1冊になっています。
関連書:
主な目次
日本語版への序 トム・エリク・アーンキル
第Ⅰ部 スーパービジョンの基本事項
第1章 職場におけるスーパービジョンの役割
第2章 学習プロセスとしてのスーパービジョン
第3章 リフレクションの方向づけ
第4章 対話的関わり
第Ⅱ部 実践と方法
第5章 スーパービジョンを実施する際の条件
第6章 オリエンテーション(志向)
第7章 アクション・メソッド(非言語的メソッド)
第Ⅲ部 スーパービジョン関係
第8章 個 人
第9章 コミュニティ
第10章 グループ
第11章 管理職(マネージャー)
まえがき
本読者の皆様へ
本書は,主に専門家であるスーパーバイザーやスーパービジョンを学んでいる学生のために書かれたものですが,スタッフに対して「日常的なスーパーバイザー」の役割を果たしている多くの管理職にも手にとっていただけることを願っています。この本は,スーパービジョンの基礎から実践までを解説する実践的なハンドブックとして構成されています。中心となる考え方は,構成主義的な学習の理論,ジョン・デューイJohn Deweyの経験主義哲学,対話に関する理論などに基づいています。また多くの場面で,ソシオメトリーやサイコドラマのみならず,解決志向やリソース指向の手法も活用しています。私たちは,できるだけスムーズで読みやすい文章を書くことを目指しており,そのために出典を直接示していません。本書における多くのアイデアがどこから,そして誰から得られたかを示すために,文献や資料の概要を巻末に掲載しています。
本書の第Ⅰ部では,スーパービジョンの基本である「学習」「リフレクション」「対話的な相互作用」を取り上げています。第Ⅱ部では,スーパービジョンの実践と手法に焦点を当てています。第Ⅲ部では,さまざまなスーパービジョンのタイプとそれぞれの特徴について詳しく説明しています。本文中の例はすべて架空のものですが,私たちが仕事で実際に遭遇した状況や事例に基づいています。私たちが効果的だと判断した複数の手法を本書のさまざまな章で紹介していますが,全体として“スーパーバイザーのためのツールボックス”のようなものとなっています。私たちが説明する手法は,多くの専門分野で使用されているものであり,人類の長い歴史を超えて伝統となってきたものです。
ダイアロジカル・スーパービジョンは,アレタイ(Aretai)社が絶え間なく行ってきた専門的努力とその成果についての考察と検証の賜物です。私たちは学習するコミュニティとして自覚しながら活動することに努め,共有される対話を追い求めていくことに努めます。そして,そのプロセスにおいて,私たちは急ぐことなく,実験的に参加者すべての視点を深め,新たな考えを発展させていくことができるのです。私たちは,自分自身の経験を豊かにして,一人ひとりの思いを超えた,より大きくより多様なものを共に創り上げていく可能性にこそ価値があるということに気づいたのです。本書は,執筆者全員が企画の段階から参加して内容を練り上げたものであり,まさに共創の一冊となっています。
原書であるフィンランド語版は2011年に出版されました。厳しい目で校正してくださった方々に感謝いたします。Harri Hirvihuhta氏は,初期の段階から本書の「ゴッドファーザー」でした。Harri氏は私たちの原稿を深く掘り下げ,私たちが自分たちの意見を述べる自信を与えてくれました。本書で紹介する多くのアイデアは,本書のさまざまなテーマを発展させるLiisa Valve-Mantyla氏のスーパービジョンによってもたらされました。Liisa氏は厳しくも建設的なコメントによって,私たちが調査的な展望と多様な考え方を失わないようにしてくれました。Liisa Raina氏は,彼女が見知らぬ作家の寄稿文の,特にコミュニティ・スーパービジョンの章に焦点を当て親切に読んでくれました。彼女は,多くの鋭い観察と質問によって,私たちの考えを広げてくれました。Anna Lansitie氏は,スーパーバイジーとして,また資格を持ったスーパーバイザーとしての観点から文章についてコメントをくれ,私たちが明確に表現できていることと,さらに解決しなければならないことを強調してくれました。また,本書の理念となる内容や言語表現についても貴重なご意見をいただきました。Tuuli Hirvilammi氏は,私たちがもはや完全に気づかなくなっていた段階で,私たちの文章を手直ししてくれました。最後に,巨匠Sara Heinamaa氏は,その自信に満ちたスタイルのセンスと,素晴らしく論理的なウィットで,私たちの本を洗練させてくれました。また,私たちのフィンランドの職場文化への探検を共にしてくれたスーパーバイジーのみなさんにも感謝したいと思います。
フィンランド語版は,フィンランドにおける専門的なスーパービジョンの分野で好評を得ました。今でも内容のほとんどは適切であると考えていますが,私たちは対話についての理解を深めてきましたので,英語版にはいくつかの新しい洞察を盛り込みたいと考えています。その中でも最も重要なのは,スーパーバイザーが自らの経験や行為を用いてスーパーバイジーと対話するためのさまざまな方法をより明確に理解することです。さらに,主に経済成長,冷酷な競争,個人の業績を称えることが主流となっている現在の職場文化とは根本的に異なる職場文化を創造するために,対話が重要であることをより強く強調しています。私たちは今,かつてないほどに経済的,政治的,生態学的な危機が絡み合った世界で生きています。これらの危機は,多くの専門家の日常業務にますます大きな影響を与えています。私たちが直面している課題にうまく対処するためには,スタッフ一人ひとりのスキルと知識を活用する必要があります。また,異分野の専門家が力を合わせ,現代社会の複雑な現象を共に理解するためのネットワークを構築し,出会いを促進することも必要です。このような作業は,対話がスタッフの基本的なスキルとなり,より広く普及しなければ成功しないでしょう。
英語版の作成にあたっては,原著者のグループに加えて,Katriina Lehti氏がKai Alhanen氏とともに文章の一部を書き直してくれました。特に,第4章の「対話的関わり」は,私たちの対話に対する理解の深まりを反映し修正しました。また,英語の文章を準備し,推敲してくれたHelena Lehti氏とDonna Roberts氏にも感謝の意を表したいと思います。
本のデザインを担当してくれたVappu Rossi氏と,印刷用に本をレイアウトしてくれたAuli Kurvinen氏にも感謝します。さらに,テキストの最終版をチェックしてくれた同僚のJanne Kareinen氏,Tomi Lamppula氏,Pekka Lavila氏の協力にも,大変感謝しています。
本監訳者あとがき
ここでは,私たちの出会いから本書出版に至るまでの道のり,そして,私たちが感じている本書の意義についてお伝えできればと思います。
私たちは,精神保健医療福祉や教育の分野に身をおく対人援助職者です。それぞれの現場でさまざまな困難に直面し,解決策を模索する中で「対話実践」について学習する機会を得て,そこで出会いました。今,精神保健医療福祉や教育の場で注目を浴びている「オープンダイアローグ」や「未来語りのダイアローグ」を学ぶ場です。私たちは,対話を学び実践する中で,すでに対話のもつ力を十分に実感し,さらに多様な場でその力を発揮できるはずだということを確信していました。
そんな中,監訳者の一人であり,対話文化が根づいているデンマーク在住の片岡豊より本書の紹介を受けました。テーマにある「ダイアロジカル」という言葉に惹かれたのは言うまでもありません。そして,対話に興味のある仲間とともに,自主勉強会という形で本書を読み進め理解を深めることにしました。また,勉強会に先立ち,監訳者の2名(石川真紀,川田美和)は,北欧のスーパーバイザーから実際にダイアロジカル・スーパービジョンを受ける経験もしました。それはグループ・スーパービジョンの形で実施されましたが,対話の原則である「聞くこと」と「話すこと」を分ける構造が保たれ,常に安心・安全の中で内的な対話が豊かに広がる体験をしました。そしてスーパーバイザーからはもちろん,他のスーパーバイジーからも多くの学びを得る貴重な機会になりました。自主勉強会では,他の学習者からたくさんの刺激を受け,実際に体験したスーパービジョンをより深く意味づけする機会になるとともに,理論と経験に裏づけられた非常に実践的な内容に感銘を受けました。そして,対人援助職者のみならず,さまざまな組織の管理者や後輩育成にあたる人々に本書の内容を知って頂きたいと強く感じました。これが本書出版のきっかけです。
翻訳にあたっては,北欧と日本の文化の違いもあり苦労したことも多かったのですが,本書に掲載されている具体的な事例は,ほぼ同じ現象が日本でも生じており,仕事をしていく上での困難に文化の隔たりはないことを痛感しました。このことが自主勉強会でもしばしば話題となり,そして,それが本書の日本語出版を勇気づけてくれたように思います。
ハーバード大学院教員であるキーガンKegan, R.とレイヒーLahey, L.は,「人が仕事で燃え尽き状態に陥る最大の原因は,仕事の負担が重すぎることではない。その要因とは,成長を感じられずに長く働き続けることだ」(ロバート・キーガン,リサ・ラスコウ・レイヒー(中土井僚監訳,池村千秋訳)『なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか』英治出版,2017.[序章より])と言っています。
VUCA(Volatility;変動性,Uncertainty;不確実性,Complexity;複雑性,Ambiguity;曖昧性)時代と言われる今,急速な変化を遂げる社会を背景に,多くの現場で複雑かつ多様化するクライアントのニーズへの対応に追われています。災害大国でもある我が国は,日常業務に加えて,ときに突発的な事態への対応を迫られることもあり,常に葛藤やストレスにさらされていると言っても過言ではないでしょう。そのような中,成長を感じながら仕事を続けるためには,成長を支援される枠組みや仕組みが必要です。スーパービジョンは,間違いなくその1つです。さまざまな現場で,組織の目的達成のために仕事を担っている全ての人にとって,スーパービジョンは必須だと考えます。
残念ながら今の日本ではスーパービジョンの文化が根づいているとは言えません。また,実践されているとしても,指導的で権威的な古いタイプのスーパービジョンである可能性もあります。1人でも多くの方に,安心・安全を土台とした双方の成長につながるダイアロジカル・スーパービジョンを知っていただきたいです。同時に,本書が日本のスーパービジョン文化の土台づくりの一端を担えることを願いつつ,あとがきとさせて頂きます。
本書は多くの方々のご協力で完成しました。仮訳を元に行われたオンライン自主勉強会に参加された32名のみなさまとの相互作用でアイデアが広がり翻訳書の必要性も生じました。また,この勉強会は,事務局となってくださった,特定非営利活動法人ダイアローグ実践研究所(DPI)蓬田氏がいなければ実施できませんでした。原著者のアルハネン(Alahanen, K.)氏,デンマークのスーパービジョン実践者ソーレンセン(Soerensen, K.)氏は快く特別講師を引き受けてくださり,本書のより深い理解を助けてくださいました。同じくデンマークの実践者であるソーレンセン(Soerensen, J.)氏は,特別講師のみならずオンラインでのスーパービジョンを実施してくださり,体験を通した理解と実践への興味が高まりました。翻訳に関しては,ご多忙中で各章を共に訳してくださった高瀬氏,小野氏,梶原氏,水谷氏,また全体へ目を通し貴重なアドバイスを下さった翻訳家の早野氏,膨大な作業で複数の監訳者の意見をまとめて指摘や修正くださった山内氏をはじめとした出版社のみなさま,誰1人欠けても完成には辿り着けませんでした。全ての方々に深く感謝申し上げます。
川田美和・石川雅智・石川真紀・片岡豊
著者略歴
Kai Alhanen(カイ・アルハネン)
哲学修士・神学博士(国立ヘルシンキ大学)。アレタイ社(Aretai Ltd.),ダイアログアカデミー・マネージャー。フィンランド生まれのダイアローグ実践理論の代表者の一人。”Dialogical leadership”,”Timeout”など多数の著作活動。
フィンランド政府のシンクタンク機関であるSITRAの顧問として,フィンランドの行政部門,教育・福祉部門などの公共機関と民間企業に幅広くダイアローグを基盤としたカウンセリングやコーチングを行っている。精神医療のオープンダイアローグのヤーコ・セイックラ,教育・福祉部門のAD(アンティシペーション・ダイアローグ)のトム・アンキルに並ぶフィンランド発信のダイアローグ実践理論の第一人者として認められている。
また,ロシアのウクライナ侵攻を背景に,カイ・アルハネン氏は,上記の政府シンクタンク機関のSITRAと連携して,”Democracy Defense Dialogue”(デモクラシーを守るダイアローグ)というテーマを掲げて,オンラインによる国際的なダイアローグによる平和活動を推し進めている。
主著書:Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa. Gaudeamus, 2007./ Practices and Thought in Michel Foucault’s Philosophy. BoD, 2018., John Deweyn kokemusfilosofia. Gaudeamus, 2013./ John Dewey’s Ecology of Experience. BoD, 2018., Dialogi Demokratiassa. Gaudeamus, 2013./ Dialogue in Democracy. BoD, 2019.
Anne Kansanaho(アンネ・カンサナホ)
スーパーバイザー兼トレーナー,アレタイ社(Aretai Ltd.)。
Olli-Pekka Ahtiainen(オリ・ペッカ・アーティアイネン)
スーパーバイザー兼トレーナー,アレタイ社。
Marko Kangas(マルコ・カンガス)
スーパーバイザー兼トレーナー兼CEO,アレタイ社。
Katriina Lehti(カトリイナ・レーティ)
スーパーバイザー兼トレーナー,アレタイ社。
Tiina Soini(チーナ・ソイニ)
研究ディレクター,フィンランド国立タンペレ大学。
Jarkko Soininen(ヤルコ・ソイニネン)
スーパーバイザー兼トレーナー,アレタイ社。
推薦者略歴
Tom Erik Arnkil(トム・エリク・アンキル)
フィンランド人。フィンランド国立保健福祉研究所 元研究教授(2015年定年退職)。NPO法人ダイアローグ実践研究所(DPI)理事。オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン(ODNJP)名誉会員
【日本語出版】著作:あなたの心配事を話しましょう(高橋睦子訳,日本評論社,2018),ダイアロジカル・スペース(浅井伸彦訳,NPO法人ダイアローグ実践研究所,2019),共著:オープンダイアローグ(高木俊介・岡田愛訳,日本評論社,2016),開かれた対話と未来(斉藤環監訳,医学書院,2019)
*トム・アンキル氏はヘルシンキ大学やフィンランド国立保健福祉研究所においてネットワーク・ダイアローグおよび「未来語りのダイアローグ」の開発に携わるかたわら,古代ペルシャを舞台にした一連の歴史小説の作者として活躍。全6巻からなるシリーズ最終版 “The book of Benjamin Aamoksenpoja” を2022年8月に出版。
監訳者略歴
川田美和(かわだ・みわ)
高知県生まれ,兵庫県立大学看護学部(精神看護学)教授。博士(看護学)。看護師・保健師・精神看護専門看護師。
主な著書:『長期入院患者のおよび予備群への退院支援と精神看護』(分担執筆,医歯薬出版会,2008),『精神看護スペシャリストに必要な理論と技法』(分担執筆,日本看護協会出版会,2009),『精神看護実習ポケットブック』(分担執筆,精神看護出版,2010)ほか
石川雅智(いしかわ・まさとも)
ニューヨーク生まれ,元千葉大学大学院医学研究員精神医学特任准教授,弥生会旭神経内科リハビリテーション病院・学而会木村病院非常勤務医師。東洋史学修士,医学博士,日本精神神経学会専門医・指導医,認知症診療医。
主な著書:『新体系 看護学全書 精神看護学② 精神障害をもつ人の看護』(分担執筆,メヂフレンド社,2017,2019,2021)
主な論文: “High occupancy of sigma-1 receptors in the human brain after single oral administration of fluvoxamine: A PET study using [11C]SA4503”. Biol Psychiatry, 62: 878-883.
石川真紀(いしかわ・まき)
東京生まれ,医学修士,精神保健指定医,千葉県こころセンター(精神保健福祉センター)技監兼次長。
主な著書:『新体系 看護学全書 精神看護学② 精神障害をもつ人の看護』(分担執筆,メヂフレンド社,2017,2019,2021)
主な寄稿論文:「精神保健福祉センターの訪問支援におけるオープンダイアローグ的対話の試み」(精神科治療学,2018)など
片岡豊(かたおか・ゆたか)
東京生まれ,元エグモント・ホイスコーレン教員。修士(国立オーフス大学思想史学科・哲学部)
主な寄稿記事:「リハビリテーション」(社会福祉法人鉄道身障者福祉協会発行)『デンマークにおけるインクルーシブな就労政策』(2006. 12),『デンマークにおける特別支援教育制度』(2009. 8・9),『インクルーシブな学校,エグモントホイスコーレン』(2014. 8・9, 10, 12, 2015. 01),『障害者の差別について──デンマークの現状』(2016. 2・3)など
翻訳:『クローさんの愉快な苦労話』(ぶどう社,1994)
訳者一覧
第1・2章
高瀬玲:医療法人東峰会,関西青少年サナトリューム
第3・4章
片岡豊:特定非営利活動法人ダイアローグ実践研究所(DPI)
小野博史:兵庫県立大学看護学部看護基礎講座
第5~7章
梶原友美:神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域
川田美和:兵庫県立大学看護学部生涯広域健康講座/精神看護
第8~10章
石川雅智:旭神経内科リハビリテーション病院・学而会木村病院
石川真紀:千葉県こころセンター(精神保健福祉センター)
第11章
水谷裕子:特定非営利活動法人アーモンドコミュニティネットワーク
翻訳アドバイス
早野ZITO真佐子:医療福祉ジャーナリスト・通訳・翻訳
「遠見書房」の書籍は,こちらでも購入可能です。

最寄りの書店がご不便、あるいはネット書店で在庫がない場合、小社の直販サービスのサイト「遠見書房⭐︎書店」からご購入ください(store.jpというECサービスを利用しています)。商品は在庫のあるものはほとんど掲載しています。