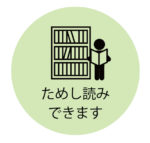公認心理師の基礎と実践⑰――福祉心理学 第2版
公認心理師の基礎と実践⑰
――福祉心理学 第2版
野島一彦・繁桝算男監修
(愛知学院大学)中島健一 編
本体2,800円(+税) A5判 並製 228頁
C3011 ISBN978-4-86616-212-6

福祉分野への心理支援を充実させる
福祉心理学関連の法・制度・用語等はもちろんのこと,福祉分野における心理支援のあり方について,実力のある実践家となるために実践事例を通して学ぶ1冊。
真に,クライエントのためになることを考えられる心理職になるために。
目 次
第1部 福祉対象者への心理支援の必要性とあり方
第1章 社会福祉の展開と心理支援 大迫秀樹
第2章 総論:生活を支える心理支援 片岡玲子
第3章 暴力被害者への心理支援 米田弘枝
第4章 高齢者への心理支援 加藤伸司
第5章 障害・疾病のある人への心理支援 白石雅一
第6章 生活困窮・貧困者への心理支援 中島健一
コラム 外国にルーツをもつこどもたちは幸せだろうか? 松本真理子
コラム 多文化を知る帰国子女だからこその悩みとその支援 松丸未来
第2部 福祉心理学的心理支援の実際
第7章 児童虐待への心理支援の実際 松﨑佳子
第8章 こどもと親への心理支援の実際 増沢 高
第9章 認知症高齢者の心理支援の実際 下垣 光
第10章 ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際 徳丸 享
第11章 精神障害者への心理支援の実際 大塚ゆかり
第12章 家族・職員への心理支援の実際 長野恵子・利光 恵・藤岡孝志
第13章 福祉・介護分野での多職種協働(IPW)と心理職の位置づけ 城戸裕子
第14章 IPW実践事例報告 川瀬里加子・中村考一・平井裕一・牛山卓也・太田裕子
コラム 性的マイノリティの人々への心理支援──性的指向,ジェンダーアイデンティティの理解を基盤に 大賀一樹
コラム 保育所や幼稚園での「不適切保育」に対して私たちができること 原口喜充
はじめに
本巻は,公認心理師をめざす学生がその養成カリキュラム「福祉心理学」で『学ぶべき内容』を網羅した教科書として構成されている。したがって,公認心理師になるにあたっての必要な福祉心理学関連の法・制度・用語等はもちろんのこと,福祉分野における心理支援のあり方について真に実力のある実践家となるために実践事例を通して学び,考えていただく内容としている。
本巻は,全14章の全体を通して法・制度等解説と実践事例の紹介を盛り込んでいるが,大きくは第Ⅰ部「福祉対象者への心理支援の必要性とあり方」は総論編,第Ⅱ部「福祉心理学的心理支援の実際」は実践編として濃淡をつけている。
第Ⅰ部第1章と第2章は総論編の中でも総論に位置づけられる。第1章では我が国の福祉の歴史と現在の制度の概要を学び,福祉対象者への心理支援の必要性・重要性および課題を巨視的な視点で学んでいただく。第2章では第1章を受けて各福祉分野における心理支援の必要性・重要性および課題を個別に概説しており,理解を深めていただく。この2つの章を通して福祉分野全体を俯瞰的に捉えつつ必要な心理支援とはどのようなものかについて考えていただきたい。第3章から第6章は,「第3章 暴力被害者」「第4章 高齢者」「第5章 障害児者」「第6章 生活困窮者」についての心理支援総論を分野別に詳しく紹介している。福祉分野は幅広く,支援対象者もさまざまである。したがって,支援が必要な内容もさまざまではあるが,一方で人間としての共通性・人が安心・安定して生活することの共通性はある。学習を通して,読者それぞれの理解・思いを深めていただきたい。
第Ⅱ部は第Ⅰ部を受けて,では「福祉心理学」を学んだ読者は実際にどう考え何をしたらよいのか,の参考となる実践内容を多く含んだ構成となっている。第7章と第8章は第3章,第9章は第4章,第10章は第6章,第11章は第5章と絡めながら学習するとよいかもしれない。第12章は,福祉分野における家族・職員への心理支援の実際を紹介している。公認心理師は支援の質を深めるだけではなく,幅を広げる視点も重要である。第13章と第14章では福祉・介護分野での多職種協働を各種実践事例を含めて取り上げている。職場において孤立しないことは公認心理師自身にとって必要なことであり,支援対象者にとってもきわめて重要なことである。
福祉分野における心理支援については,これからの発展が期待される。従来型の白衣を着た相談室カウンセラーというスタイルでは対応できない分野も多い。しかし,福祉職・介護職のお手伝いに埋没してはいけない。支援対象者の生活全体を視野に入れつつ生活に介入しつつ,しかしながら心理専門職としての『専門性の旗』はきっちりと揚げた業務のあり方を開発していくことが今後の大きな課題である。
そして,支援対象者本人に対しては,生活の場にとどまらない環境軸および,将来を見据えた時間軸を持って支援にあたっていただきたい。また,本人のみならず,家族に対する支援,福祉施設等の職員に対するストレスマネジメントも大きな役割となる。
本シリーズ・本巻で学び公認心理師となり実践現場で活躍することになる読者諸氏の臨機応変・創意工夫・初志貫徹に期待するところである。
2024年9月
中島健一
監修 野島一彦(のじまかずひこ:九州大学名誉教授・跡見学園女子大学名誉教授)
繁桝算男(しげますかずお:東京大学名誉教授・慶應義塾大学)
編者略歴
中島健一(なかしまけんいち)
愛知学院大学心身科学部心理学科・大学院心身科学研究科心理学専攻教授,公認心理師・臨床心理士
九州大学大学院教育学研究科博士後期課程教育心理学専攻を修了。九州大学教育学部附属障害児臨床センター助手,日本社会事業大学社会事業研究所専任講師,厚生省老人保健福祉局老人福祉専門官,日本社会事業大学教授を経て,2015年より現職。2002年4月~2004年3月までは高齢者痴呆介護研究・研修東京センター副センター長も併任。社会福祉学博士。
主な著書:『認知症高齢者の心理劇「感ドラマ」』(ミネルヴァ書房,2015),『高齢者動作法』(誠信書房,2012),『ケアワーカーを育てる「生活支援」実践法』(中村考一との共著,中央法規出版,2005),『痴呆性高齢者の動作法』(中央法規出版,2001),『高齢者のこころのケア』(長野恵子らとの共著,小林出版,1999),『新しい失語症療法:E-CAT』(中央法規出版,1996)ほか多数
執筆者一覧
中島 健一(なかしまけんいち:愛知学院大学心身科学部心理学科)
大迫 秀樹(おおさこひでき:九州女子大学人間科学部人間発達学科)
片岡 玲子(かたおかれいこ:立正大学心理臨床センター)
米田 弘枝(よねだひろえ:元 立正大学心理学部)
加藤 伸司(かとうしんじ:東北福祉大学総合福祉学部福祉心理学科/認知症介護研究・研修仙台センター)
白石 雅一(しらいしまさかず:宮城学院女子大学教育学部教育学科)
松﨑 佳子(まつざきよしこ:広島国際大学心理科学研究科)
増沢 高(ますざわたかし:子どもの虹情報研修センター)
下垣 光(しもがきひかる:日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科)
徳丸 享(とくまるあきら:立正大学心理学部臨床心理学科)
大塚ゆかり(おおつかゆかり:山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科)
長野 恵子(ながのけいこ:西九州大学名誉教授)
利光 恵(としみつめぐみ:西九州大学子ども学部心理カウンセリング学科)
藤岡 孝志(ふじおかたかし:日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科)
城戸 裕子(きどゆうこ:愛知学院大学心身科学部健康科学科)
川瀬里加子(かわせりかこ:医療法人清和会新所沢清和病院)
中村 考一(なかむらこういち:社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター)
平井 裕一(ひらいゆういち:愛知学院大学心理臨床センター)
牛山 卓也(うしやまたくや:社会福祉法人嬉泉)
太田 裕子(おおたひろこ:愛知学院大学心理臨床センター)
コラム:
松本真理子(まつもとまりこ:名古屋大学名誉教授)
松丸 未来(まつまるみき:東京認知行動療法センター)
大賀 一樹(たいがかずき:日本女子大学ダイバーシティ委員会アドバイザー)
原口 喜充(はらぐちひさみ:近畿大学九州短期大学)
「遠見書房」の書籍は,こちらでも購入可能です。

最寄りの書店がご不便、あるいはネット書店で在庫がない場合、小社の直販サービスのサイト「遠見書房⭐︎書店」からご購入ください(store.jpというECサービスを利用しています)。商品は在庫のあるものはほとんど掲載しています。