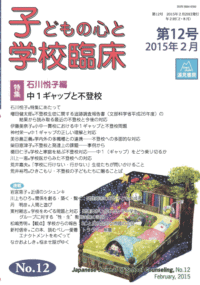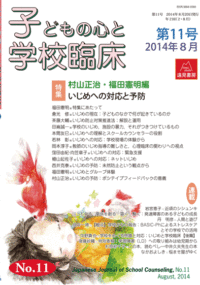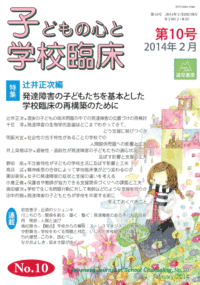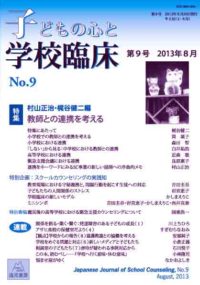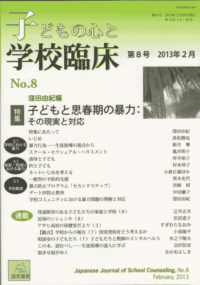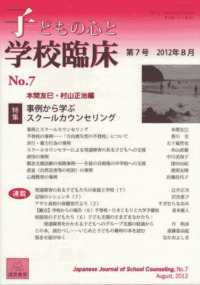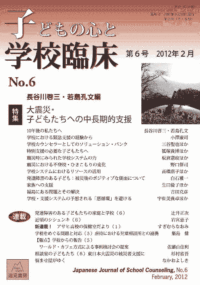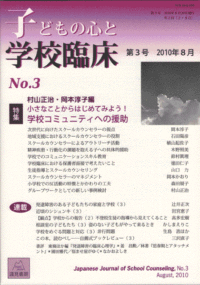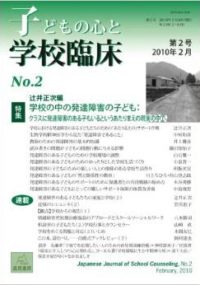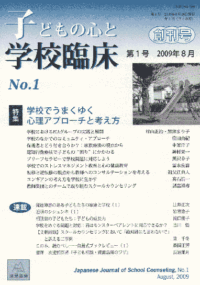思春期・青年期の精神分析的アプローチ――出会いと心理臨床
乾吉佑著(3,400円+税)ISBN978-4-904536-06-3◆本書は,著者が臨床経験の多くを費やしてきた思春期から青年期にかけての若者と,その保護者などを交えた心理療法の実際をまとめた論集です。著者乾先生の技法的な中核は,精神分析的心理療法ですが,それだけではなく,短期療法や家族療法,親子並行面接法などもケースによっては用いており,クライエントの状況やニーズに合わせた幅広い心理療法が行っています。本書には,それらを用いて治療された,強迫性障害,自閉症,境界性パーソナリティ障害といった疾患ベースのケーススタディ論文,あるいは学生相談や病院臨床,個人開業といった多彩な臨床現場ベースの論文が所収され,事例と技法について具体的な解説がなされています。